はじめに
娘の成長に不安を覚え、毎日のように発達に関して検索していた時期がありました。
「自閉症の初期サイン」という言葉を何度も目にし、そのたびに不安に駆られる毎日。
娘(のぞみ)が自閉症として3歳を迎えた今、当時を振り返れば、
「自閉症の初期サイン」に当てはまる部分もあれば、当てはまらない部分もたくさんありました。
つまり「これがあったから自閉症・これがなかったから自閉症じゃない」と一概に言えるサインは、なかなか見つけられるものではないのかもしれません。
私自身、当時は情報に振り回されて苦しい思いもしましたので、この記事では「サイン」という形ではなく、わが家の娘(のぞみ)が療育センターに繋がるまでの「発達の変遷(特に運動面)」を一例としてご紹介したいと思います。
同じように悩む方にとって、医療機関に相談する一歩や安心の材料になれば嬉しいです。
娘の運動発達の変遷(0歳~2歳)

●首座り
一般的には3~4か月頃と言われています (※参照:公的機関の資料/下部リンク)
首が座り始めたのは生後2か月ごろでしたが、不安定さが長く続き、のぞみの場合完全に安定したのは5か月を過ぎたころでした。
●寝返り・おすわり
一般的には5~7か月頃と言われています
保育園に通い始めた0歳11か月で習得。
発達の早い子と比べて、既に半年ほどの差がありました。
●ずりばい・はいはい
一般的には8~10か月頃と言われています
のぞみは、おすわりができるようになってから、比較的はやくずりばいを開始し1歳ごろに少しずつできるようになってきました。
最初は後ろへ下がる動きから始まり、徐々に前進できるようになりました。
1歳半ごろに「はいはい」の形になりました。
●つかまり立ち
一般的には9~10か月頃と言われています
1歳2か月で大人の介助を得ながら数秒立てるように。
1歳4か月で小児ぜんそく入院したのですが、ベビーベッドの柵をつかんでしっかり立てるようになって戻ってきました。
●立つ・歩く
一般的には11~1歳4か月頃と言われています
自力で歩けるようになったのは2歳2か月。
療育相談センターでPTリハビリ(理学療法)を始めてからのことでした。
最初は手をつないでの歩行練習から始まり、2歳半には一人で歩けるように。
そこを皮切りに、滑り台に挑戦するなど運動能力が飛躍的に伸びていきました。
医療機関との関わりと受診までの流れ
娘は低出生体重児(2395g)で生まれたため、出産をした総合病院の小児科に定期通院をしていました。
体重の伸びに加えて徐々に「運動面での遅れ」を指摘されるようになり、
血液検査や聴力検査などを受け、他の病気の可能性を一つずつ除外していきました。
その後、市の1歳半健診を迎えましたが、すでに主治医から療育を勧められていたため、
健診は簡略化され「療育相談センター」への受診へとつながりました。
療育センターへ繋がるまでに感じたこと
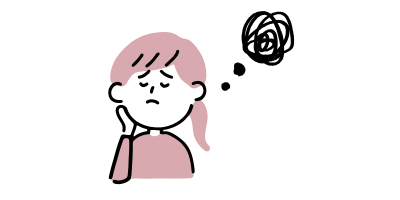
日々の育児の中で私はインスタなどのSNSを見るたびに「なぜのぞみは他の子とここまで発達の差が開いてしまっているのか」という思いに押しつぶされそうになり、昼夜WEBで検索ばかりしていました。
ネットにも散見され、医療従事者の方や、その他大勢の方から励ましてもらえる言葉
「発達には個人差がある」
それは紛れもない事実です。その言葉に助けられたこともあります。
しかし、そうと言っても、分かってはいるけれどその「個人差」が完全なる安心材料になることはなく、率直に言うと、私にとっては不安の方が大きいと感じました。
「個人差があるから分からない」その条件こそが、「のぞみの本当を知りたい」という答えを、遠ざけてしまっているような気がしてたからです。
ただ振り返ると、悩みは常に変わり続けていました。
半年前は「おすわりができない」と悩んでいたのに、半年後には「歩けない」に変わっている。
悩みは尽きませんでしたが、確かに前進している部分もありました。
まとめ:同じ悩みを抱える方へ
「自閉症の初期サイン」に当てはまるかどうかで悩むのは、とても辛いことだと思います。
そのため、ここで書いたのはあくまで「のぞみの運動発達の変遷」にすぎません。
一般的な発達表を見るのではなく「半年前ののぞみと比べて、今ののぞみがどう変わったか」という視点で娘を見るようにしていくと、心が少しだけ軽くなった気がしたので、マイルールとしてそれを一つ意識するようにしてみました。
その上で、半年経っても状況が変わらないときは、医療機関に相談することもきっと大きな一歩になるはずと思います。
調べること、半年前と比べてどう変化したか振り返ること、そして専門機関に相談すること。
この三つの軸を持つことで、不安に少し光が差すと私は感じています。
同じように悩む方にとって、この記録が小さな安心や前進のきっかけになれば幸いです。
筆者や娘の詳細プロフィールは、よろしければ下記の記事をご覧ください。
●関連記事
最新記事
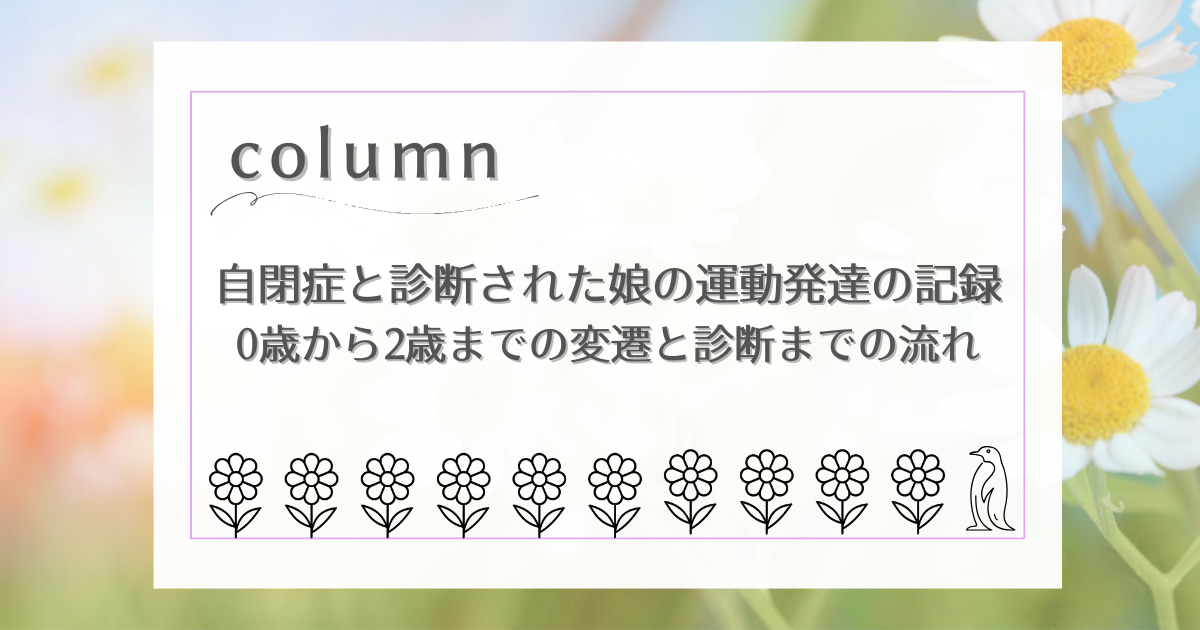
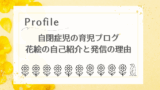
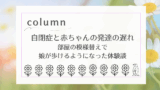
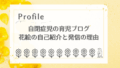
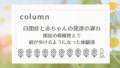
コメント